

ースギ材の活用に高まる可能性ー
(財)農林科学研究所
● (財)農林科学研究所(野村隆哉所長)が呼びかけた燻煙熱処理研究会・研修会が
9月29、30日の2日間にわたって京都府宇治市五ヶ庄の京都大学木質科学研究所
で開催された。
燻煙熱処理については、本誌第13号で、創刊2周年記念企画特集として、野村氏
の研究成果と監修をもとに「スギ材を生かすための挑戦~スギ材を生かす燻煙熱処理
加工」の論文を掲載し、挑戦をよびかけた。
現在、一部の製材所や竹炭生産のための前処理として実際に燻煙熱処理が行われて
いるが、実用が本格化して広がるのはこれからで、杉材の需要を広げ、山林を育てる
最も有効な方策として期待されている。
同財団が活動をはじめるまでは、野村氏が主宰する木文研究会の分科会として燻煙
熱処理研究会が持たれ、特許等の障害を乗り越えて、誰でもが手軽に実用化できるも
のをめざした研究と実践を行ってきた。
今回の研究会・研修会はそれらの成果を持ち寄って交流し、事業体として集結する
準備会として開催された。
研究会には、燻煙熱処理に取り組んでいる人たちを中心に東北から九州まで全国か
ら60余名が出席して研修と交流を行った。
●燻煙熱処理の多大な効果
1日目は研究・実践の発表を主にし、午後1時から始められた。
開会の挨拶に立った野村氏がそのまま第1テーマの「燻煙熱処理の効用と、素材そ
のものの商品化をすすめるためのシステムをどのように構築するか」と題し、燻煙熱
処理の連関に絞って話をした。
この中で野村氏は、「燻煙熱処理とは、廃材などの木を燃やした煙で燻して、木の
持っている狂い(成長応力=アテ)を軽減させ、併せて乾燥を促進させる直接加熱式
の木材乾燥法のひとつである」とした上で、ポイントとなる「煙」という混合ガスに
ついて解明した。
熱媒体としての煙の機能を説明し、炉内の混合ガスのススの量、水蒸気量が多いほ
ど、空気だけの場合より、熱を伝えやすいこと。さらに煙を媒体とすることで、その
中に含まれるススの黒体輻射熱を利用できることで、熱源から直接、物体内部に対し
て一種の電磁波としての熱を伝える「熱放射」ができ、この電磁波(遠赤外線)が木
竹材に直接吸収され、熱エネルギーに変わり、材の温度を上げる働きをする原理を説
明した。これにより従来の空気と水蒸気を熱媒体としている蒸気式木材乾燥その他の
乾燥方法よりも、効率面ではるかにすぐれている上に、材の中心部の熱処理もできる
ことを示した。 
木材のひずみの均一化については、ひずみを形成する細胞壁の中のリグニンを軟化
させる温度域にまで材内の水分温度を上昇させる燻煙熱処理で実現できることを解明
した。
また、燻煙熱処理をした木材の持つ防カビ、防腐等の効果にも言及した上で、「燻
煙熱処理の最大の長所は、木材のひずみの緩和と含水率の軽減による乾燥処理、及び
寸法安定化処理を一挙にできることである」と語った。
さらに、この方法ではどのような大径の丸太でもそのままの処理で、30~40%
の含水率にして、一定期間の自然乾燥で製材できることや、炉(カマ)次第では大量
処理もできることを語り、杉材をはじめとする木材と林業の復活と日本の文化の復興
につながるものとなることを強調した。
続けて野村氏は、現在の木材が、材料的機能だけしか語られない商品となっていて
、木材の持つ機能の全体が商品化されていない問題を指摘。
燻煙材を世に出すためには、機能の商品化をはかることと、産業連関のシステムを
つくることが必要であると強調した。
そして、素材の規格とデザイン力をつけ、ボリュームを確保する必要性を語った上
で、商品化されている炉は、ほとんど全て完成された炉とはいえないこと、小さくと
も自分でつくることの大切さを強調した。
それは、設備プラスアルファの気圧、気候、材その他の条件が絡むからで、早急に
モデルプラントとマニュアルを完成させたいとして結んだ。
●味のある商品の安定供給を
このあと、大分県林業試験場木材部の三ヶ田雅敏主任研究員による「燻煙加熱処
理による木材乾燥について」の実践報告、京竹炭の永田寛治氏の「竹炭生産における
燻煙熱処理の実際」の熱処理と炉の完成報告、松原建築設計研究所の松原秀範氏によ
る「瀬戸内文化圏構想21」と題する新しい木材連関の地域開発構想が発表された。 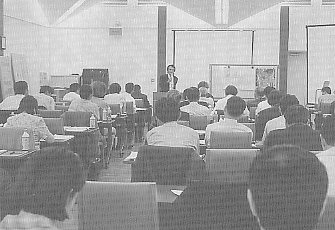
報告の最後に、木材流通の立場から㈱紅中の中村暢秀社長が、住宅着工数の増加の
なかでニセモノがつくられ、売られてきたが、もう量はいらない時代になったと語り
「本物で、厚くて、しっかりした味のある商品が求められている」「時代の転換期で
日本に合う木の家の方向に変わっている」として、山元・産地は「こういうものがほ
しかった」と言われるものを考え、開発し、1日も早く供給・品質・価格の安定した
燻煙処理材を供給してほしいと呼びかけた。
研究会では、これらの報告をもとに、各地で実践されている燻煙熱処理の実践や現
状、質疑応答などの総合討論が行われた。
引き続き午後6時からの懇親会では、野村研究室の手づくり料理を口にしながら、
参加者の盛んな交流が行われた。
2日目には、午前10時から野村研究室の横に設けられた実験用小型熱処理装置と
いくつかの炉をもとにした研究会が行われ、午後からは事業体づくりについての意見
交換を行い、各自がレポートを提出することとして閉会した。
京都大学木質科学研究所(野村隆哉)