
The Indonesia Pavilion at the first World Exposition, 1970.


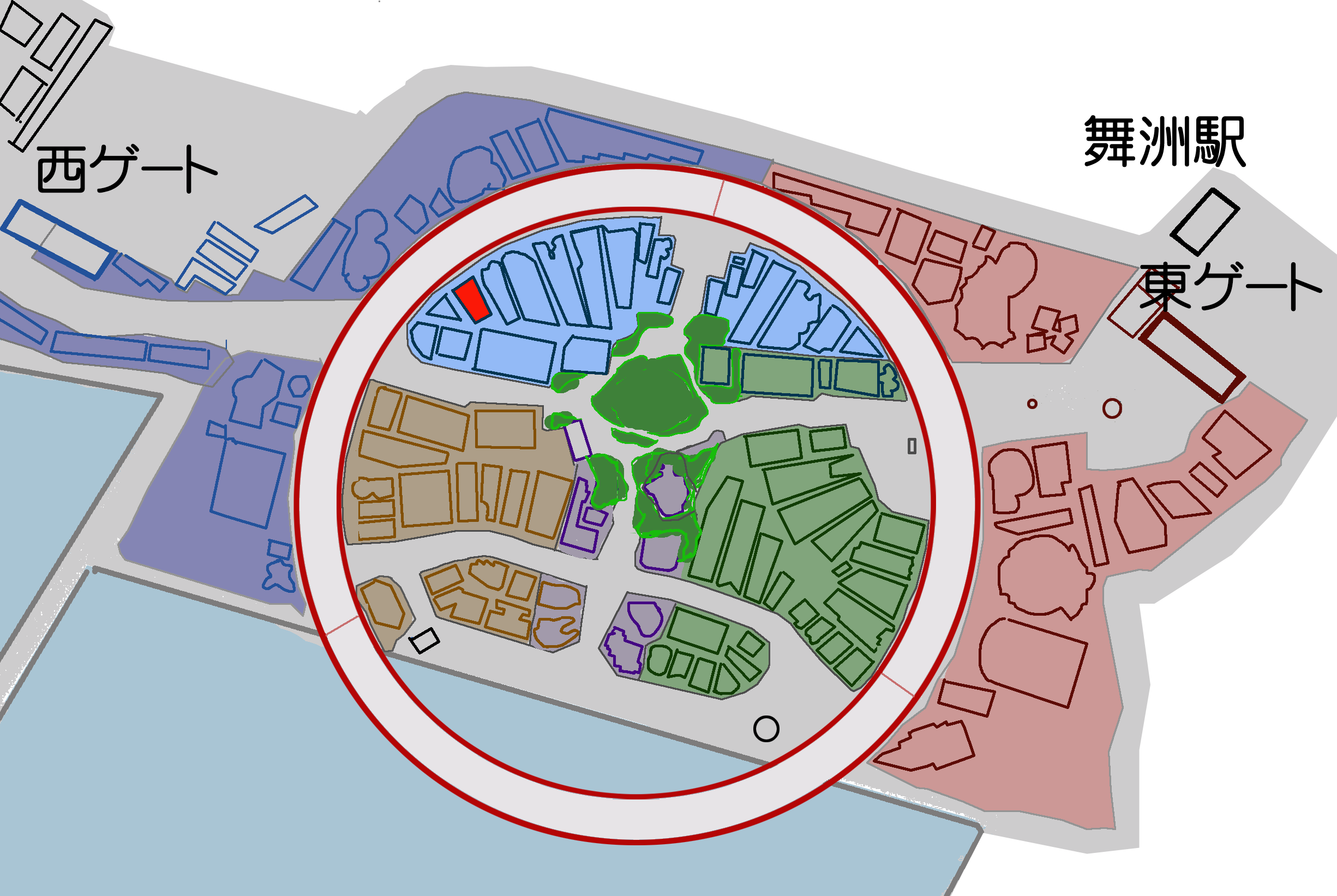
1970年の大阪万博にもインドネシア館が出展していました。当時は第2代大統領スハルト政権になって2年目で、国としてはまだ発展途上の時代でしたが、それでも100名以上のインドネシア人が来日し、パビリオンで働いていました。
私(編集者)はお祭り広場で勤務していましたが、インドネシア館が近くにあったため、仕事の前後によく立ち寄りました。そこでホステス、踊り子、警備員、事務スタッフの人たちから言葉を学び、約1か月ほどでインドネシア語の会話が自由にできるようになりました。この経験がきっかけで人生は大きく変わり、総合商社に就職して憧れのインドネシアに赴任することができました。その後は経済団体でのミッション派遣や、テレビ番組の企画などを通じてインドネシアと深く関わるようになりました。現在に至るまで、当時のインドネシア館のスタッフとの家族ぐるみの交流が続いており、来日時のホームステイ、ジャカルタでの再会、オンラインによる同窓会、近年ではSNSでのやりとりなど、交流の形は変わりながらも続いています。
また、バンドン工科大学やインドネシアの団体(Hyphen. Yogyakarta )から、1970年万博インドネシア館の研究や顕彰のための使節団を受け入れる機会もありました。こうした活動はNHKにも取り上げられ、2023年と2025年に放送されています。
2025年のインドネシア館にもすでに3度ほど訪問しましたが、1970年のパビリオンとは大きく趣が異なります。日本もインドネシアも、この半世紀で大きく変わったことを実感します。
1970年のインドネシア館では、踊り子や歌手、演奏者はいずれも選び抜かれた一流の人材で、ホステスは洗練され頭脳明晰、警備スタッフは落ち着いた屈強なタイプで、まさに一流ぞろいでした。彼らはにこやかではありましたが、過度に愛想を振りまくわけではなく、しかし一度話をすると長く親しく付き合える人懐っこさがあり、居心地の良いパビリオンでした。
建設は当時「日本一」と評された鹿島建設が担当し、インドネシアとの結びつきの深さから、同国関係者の寮も同社が建設しています。建物は鉄骨鉄筋構造で、外装には日本の杉皮が用いられていました。館内はゆったりとした設計で、多くの来場者を受け入れることができました。レストランはテーブルクロスを備えた本格的なもので、ゆっくりとインドネシア料理を楽しむことができ、毎日バリのガムランやアンクルンの演奏、ジャワ、スマトラ、カリマンタンの民族舞踊が披露されました。天皇陛下もご覧になった立派なステージでした。
一方、2025年のインドネシア館はグループごとの移動方式が採られており、多くの来場者を効率よくさばくには不向きです。また時間単位で区切られているため、スタッフとじっくり会話を交わすことは難しく、「こんにちは」と交わす程度で終わってしまいます。展示は映像が中心ですが、特に最後の部屋では映画館さながらの迫力ある映像が楽しめ、インドネシアが本来持つ文化・芸術の力を十分に発揮した内容になっています。
開会当初は控えめだったスタッフも、時間が経つにつれて雰囲気が変わり、来場者を楽しませようと一気にテンションが高まる場面も見られます。長年インドネシア人と付き合ってきた私にとっても新鮮な驚きでした。
1970年当時と2025年の現在とで大きく異なる点は多いものの、共通しているのは、やはり日本人に対する信頼と人懐っこさだと感じます。
インドネシア館は「船」をモチーフにしたダイナミックな外観を持ち、世界最多の1万7,000以上の島々から成る群島国家インドネシアを象徴しています。テーマは「自然・文化・未来の調和(Harmony in Diversity and Future Prosperity)」。2045年の先進国入りという国民の夢を船に重ね、持続的に前進する姿を表現しています。建築には米ぬか残渣(ざんさ) ・リサイクルプラスチックなどを原料とする環境配慮素材「プラナウッド(Plana Wood)」を採用し、エネルギー効率の高い照明や冷却システムを導入するなど、持続可能性を強く意識しています。