
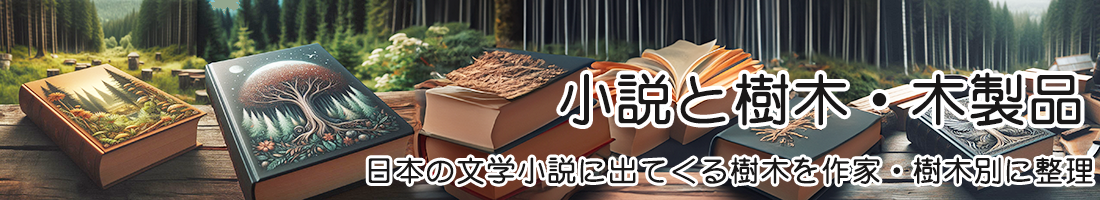
| ページ | 元樹種 | 掲載樹種 | 掲載言葉 |
|---|---|---|---|
| 6 | 樹 | 樹 | 一樹の蔭とは |
| 9 | 板ノ間 | 板の間 | 台所の板の間で |
| 13 | 葉 | 葉 | 二三枚の葉が |
| 13 | チャ | 茶の木 | 茶の木の根を |
| 13 | 根 | 根 | 茶の木の根を |
| 13 | スギ | 杉垣 | 杉垣のそばまでくると |
| 13 | スギ | 杉垣 | 杉垣の上から出たる梧桐の枝を |
| 13 | 枝 | 梧桐の枝 | 杉垣の上から出たる梧桐の枝を |
| 13 | アオギリ | 梧桐 | 杉垣の上から出たる梧桐の枝を |
| 14 | チャ | 茶畑 | 茶畑ばかり |
| 15 | チャ | 茶畠 | 茶畠の中で |
| 15 | 椽ノ下 | 椽の下 | 椽の下へ這い込んだら |
| 18 | 椽側 | 椽側 | 吾輩は椽側で |
| 20 | 椽側 | 椽側 | 南向の椽側に |
| 20 | 木枯シ | 木枯し | 木枯の吹かない |
| 20 | サザンカ | 山茶花 | 紅白の山茶花を |
| 20 | アカマツ | 赤松 | 赤松の間に |
| 25 | 枯木 | 枯木 | 枯木寒巌の様な |
| 28 | 椽側 | 椽側 | 書斎の椽側へ上って |
| 30 | 綿 | 綿 | 後で身体が綿の様になって昏睡病にかかった |
| 33 | 椀 | 椀 | 椀の底に膠着している |
| 36 | スギ | 杉垣 | 杉垣の隙から |
| 43 | トチ | トチメンボー | トチメンボーを二人前 |
| 43 | トチ | トチ | トチメンボー位なところで |
| 43 | トチ | とち | とちめんぼうは妙ですな |
| 43 | トチ | トチメンボー | トチメンボーという料理は |
| 43 | トチ | トチメンボー | トチメンボーだ、トチメンボーだと |
| 43 | トチ | トチメンボー | トチメンボーだ、トチメンボーだと |
| 43 | トチ | トチメンボー | トチメンボーが食いたかったと |
| 43 | トチ | トチメンボー | トチメンボーだと訂正とされました |
| 44 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーの材料が |
| 44 | トチメンボー | 橡面坊 | 橡面坊を種に使った |
| 49 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーの御馳走を |
| 49 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーを振り廻している |
| 49 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーでもと只今より |
| 50 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーは近頃 |
| 57 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーの亡魂を |
| 57 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーの御返礼に |
| 58 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーを御馳走した時にね |
| 58 | トチメンボー | トチメンボー | トチメンボーの復讐を |
| 60 | マツ | 松 | 鴻の台のは鐘懸の松で |
| 60 | マツ | 松 | 例の松の真下に |
| 60 | マツ | 松 | 首懸の松さ |
| 60 | マツ | 松 | 土手の上に松は |
| 60 | マツ | 松 | 首懸の松さ |
| 60 | マツ | 松 | 例の松た、何だい |
| 60 | マツ | 松 | 首懸の松は |
| 60 | マツ | 松 | この松の下へ来ると |
| 61 | マツ | 松 | 他の松では |
| 61 | 枝 | 枝 | 好い枝振りだ |
| 61 | 枝 | 枝 | 枝へ手を懸けてみると |
| 61 | マツ | 松 | この松へぶら下がっている |
| 61 | 枝 | 枝 | 枝が往来の方へ |
| 71 | 門マツ | 門まつ | 門松注目飾りは |
| 72 | 木彫 | 木彫 | 木彫の猫の様に |
| 86 | ヤナギ | 柳 | 弁じましたる柳かな |
| 92 | 木目 | 木目 | 板の木目か |
| 92 | 板 | 板 | 板の木目か |
| 105 | 椽側 | 椽側 | 椽側に寐転んで |
| 106 | ウメ | うめ | 椽側へ梅の花の印を押す位な事は |
| 106 | 椽側 | 椽側 | 椽側へ梅の花の印を押す位な事は |
| 107 | 植込 | 植込 | 植込の中を通り抜けて |
| 107 | 唐変木 | 唐変木 | 厄介な唐変木だ |
| 108 | 垣根 | 垣根 | 垣根の側へ行って |
| 111 | 椽ノ下 | 椽の下 | 椽の下へもぐり込む |
| 112 | 住居 | 住居 | わが住居の下等なるを |
| 112 | 襖 | 襖 | 襖障子の具合などには |
| 114 | 木 | 木 | 木に竹を接いだ |
| 118 | 唐変木 | 唐変木 | 高慢ちきな唐変木だ |
| 120 | 棒杭 | 棒杭 | 垣を囲らし棒杭を立てて |
| 121 | 棒 | 棒 | 天秤棒は避けざる |
| 121 | 棒 | 棒 | 天秤棒を喰う |
| 122 | 椽 | 椽 | 椽の下へ出る |
| 124 | 木像 | 木像 | 木像の様に大人しくしておらねば |
| 126 | 木魚 | 木魚 | 比丘尼が木魚の音を |
| 126 | 椽ノ下 | 椽の下 | 椽の下からでも |
| 126 | 椽ノ下 | 椽の下 | 椽の下に居るから |
| 147 | サルスベリ | 百日紅 | 百日紅が咲いていた |
| 147 | サルスベリ | 百日紅 | 百日紅が散るまでに |
| 147 | サルスベリ | 百日紅 | 百日紅が散って |
| 148 | サルスベリ | 百日紅 | 百日紅の散るまでに |
| 149 | 木像 | 木像 | 木像は仏師屋の隅で |
| 149 | 白木 | 白木 | 白木のまま |
| 149 | クリ | 栗 | 団栗だか |
| 154 | 木枯シ | 木枯し | 木枯しのはたと |
| 156 | マツ | 松 | 竜文堂に鳴る松風の音を聞かない |
| 158 | ヤナギ | 揚板 | 揚板に蹶いてか |
| 159 | ヤナギ | 柳 | 只柳行李の後に |
| 159 | 柳行李 | 柳行李 | 只柳行李の後に |
| 159 | 柳行李 | 柳行李 | 柳行李の間に |
| 159 | ヤナギ | 柳 | 柳行李の間に |
| 164 | 柳行李 | 柳行李 | 柳行李の辺から |
| 164 | ヤナギ | 柳 | 柳行李の辺から |
| 165 | 椽側 | 椽側 | 椽側を次第に遠のいて |
| 181 | 木 | 木 | 木強漢ですら |
| 183 | 小桶 | 小桶 | 小桶の尻が |
| 183 | 樽木 | 樽木 | 樽木の交叉した |
| 183 | 摺小木 | 摺小木 | 摺小木が並んで |
| 186 | 欄間 | 欄間 | 欄間と云う様な所が |
| 186 | サクラ | 彼岸さくら | 彼岸桜を誘うて |
| 188 | 板ノ間 | 板の間 | 板の間から彼を見上ぐる |
| 188 | ヤナギ | 揚板 | 揚板の上に跳ね返る |
| 189 | 板ノ間 | 板の間 | 板の間の上へ転がり出す |
| 191 | スギ | 杉垣 | 植木屋を入れた杉垣根の |
| 191 | 芭蕉葉 | 芭蕉葉 | 贋造の芭蕉葉の様だ |
| 196 | 寄木 | 寄木細工 | 寄木細工の巻煙草入から |
| 199 | スギ | 杉 | 杉箸をむざと |
| 206 | 杓子 | 杓子 | 杓子で以て |
| 210 | 天秤棒 | 天秤棒 | 天秤棒で担いで |
| 211 | 天秤棒 | 天秤棒 | 天秤棒を卸して |
| 213 | 木 | 木 | 木で鼻を括った様な |
| 215 | 枝 | 枝 | その枝へ烏を |
| 215 | ヤナギ | 柳の幹 | 柳の幹から一本の |
| 215 | ヤナギ | 柳 | 大きな柳を一本 |
| 216 | ヤナギ | 柳 | 大きな柳があって |
| 216 | ヤナギ | 柳 | 柳の影で白い女が湯を浴びている |
| 216 | ヤナギ | 柳 | 長い柳の枝に烏が一羽とまって |
| 216 | 枝 | 枝 | 長い柳の枝に烏が一羽とまって |
| 216 | 拍子木 | 拍子木 | 拍子木を入れて |
| 217 | 枝 | 枝 | 鳥が枝の上で |
| 222 | アオギリ | 梧桐 | 梧桐の緑を綴る間から |
| 226 | ウメ | 梅花形 | 梅花形の瓦の上に |
| 227 | 木 | 木 | 庭の立木を |
| 229 | 枝 | 枝 | 高い木の枝にとまって |
| 229 | 木 | 木 | 木を上って行って |
| 229 | 木登リ | 木登り | 然し木登りに至っては |
| 229 | 木 | 木 | 木登らずと |
| 229 | 木 | 木 | 高い木の枝にとまって |
| 230 | 樹 | 満樹 | 到着する時分には満樹寂として片声(へんせい)をとどめざる事がある |
| 230 | アオギリ | 青桐 | 青桐である |
| 230 | アオギリ | 梧桐 | 漢名を梧桐と号するそうだ |
| 230 | アオギリ | 青桐 | この青桐は葉が非常に多い |
| 230 | 葉 | 葉 | その葉は皆団扇位な大さであるから |
| 230 | 枝 | 枝 | 枝がまるで見えない位茂っている |
| 230 | アオギリ | 梧桐 | 梧桐は注文通り二叉になっているから |
| 230 | 葉 | 葉 | 一休息して葉裏から |
| 231 | マツ | 松 | 松滑りである |
| 231 | マツ | 松 | 松滑りと云うと松を滑る様に |
| 231 | 木登リ | 木登り | 木登りの一種である |
| 231 | マツ | 松 | 松滑りは、登る事を目的として登る |
| 231 | マツ | 松 | 松は常盤にて最明寺の御馳走をしてから |
| 231 | マツ | 松 | 松の幹程滑らない |
| 231 | 樹 | 樹 | 樹の上で |
| 232 | 椽側 | 椽側 | 椽側と平行している |
| 232 | マツ | 松 | 松の木を勢よく |
| 232 | マツ | 松 | 松樹の巓に |
| 232 | マツ | 松 | 松の木の上から落ちる |
| 232 | マツ | 松 | 松の木越をやって見給え |
| 232 | マツ | 松 | 松滑りと云うのである |
| 232 | 丸太 | 丸太 | 所々に根を焼いた丸太が |
| 235 | マツ | 松 | 松の木の皮で |
| 235 | マツ | 松 | 松皮摩擦法をやるより |
| 236 | 松脂 | 松脂 | 松脂に於てをやだ |
| 236 | 脂 | 脂 | この脂たる頗る執着心の強い者で |
| 236 | 脂 | 脂 | 松には脂がある |
| 236 | マツ | 松 | 松には脂がある |
| 237 | マツ | まつ薪 | 松薪が山の様で |
| 237 | マツ | 松 | 左の方に松を割って八寸位にしたのが山の様に |
| 238 | 板 | 板 | 四五尺の間板が余って |
| 238 | 板 | 板 | 板の高さは |
| 238 | 小桶 | 小桶 | 小桶の南側は |
| 238 | 小桶 | 小桶 | 小桶諸君の意を |
| 238 | 小桶 | 小桶 | 丸い小桶が |
| 238 | マツ | まつ薪 | 松薪と石炭の間に |
| 246 | 板間 | 板間 | 板間を見渡すと |
| 247 | 小桶 | 小桶 | 小桶を慾張って |
| 249 | 板ノ間 | 板の間 | 板の間へ上がりはせん |
| 250 | 板ノ間 | 板の間 | 流しと板の間の境にある敷居の上であって |
| 250 | 敷居 | 敷居 | 流しと板の間の境にある敷居の上であって |
| 250 | 板ノ間 | 板の間 | 板の間に上がれば |
| 250 | 鋸 | 鋸 | 鋸でこの大岩を |
| 251 | ザクロ | 遠柘榴 | 狭い柘榴口に |
| 258 | 椽側 | 椽側 | 椽側から拝見すると |
| 258 | キリ | 桐 | 桐の木が七八本行列している |
| 258 | ヒノキ | 檜 | 檜が幅を利かしているごとく |
| 258 | 枝 | 枝 | 檜の枝は吹聴する如く |
| 258 | 森 | 森 | 向こうは茂った森で |
| 258 | ヒノキ | 檜 | 檜が蓊然と五六本併んでいる |
| 258 | ヒノキ | 檜 | 檜の枝は吹聴する如く |
| 259 | 木 | 木 | 木の類は |
| 259 | キリ | 桐 | 桐の爼下駄を穿いて |
| 259 | 枝 | 枝 | この間の枝でこしらえましたと |
| 259 | キリ | 桐 | 桐はあるが |
| 259 | キリ | 桐 | 一文にもならない桐である |
| 259 | キリ | 桐 | 玉を抱いて罪ありと云う古語があるそうだが、これは桐を生やして銭なしと云っても然るべき |
| 259 | キリ | 桐 | 桐の方で催促しているのに |
| 259 | 逆茂木 | 逆茂木 | 乱杭、逆茂木(さかもぎ)の類は |
| 259 | 乱杭 | 乱杭 | 乱杭、逆茂木の類は |
| 260 | キリ | 桐 | 桐の木を去って檜の方に進んで来た |
| 260 | キリ | 桐 | 桐畠に這入り込んできて |
| 260 | ヒノキ | 檜 | 檜のある所は |
| 260 | ヒノキ | 檜 | 桐の木を去って檜の方に進んで来た |
| 261 | 植物園 | 植物園 | 植物園かと思いました |
| 262 | キリ | 桐 | 桐畠の方で |
| 266 | 木戸 | 木戸 | 木戸をあけて |
| 266 | 木戸 | 木戸 | 木戸を開いて |
| 266 | キリ | 桐 | 必ず桐の木の附近を |
| 268 | 樹 | 樹 | 樹下石上を宿とすると |
| 268 | 樹 | 樹 | 樹下石上とは |
| 269 | 渋柿 | 渋柿 | インスピレーションを得る為めに毎日渋柿を十二個ずつ食った |
| 269 | 渋柿 | 渋柿 | 渋柿を食えば便秘する |
| 269 | 朽木 | 朽木 | 一寸八分の朽木である如く |
| 271 | キンカン | 金柑 | 金柑頭を |
| 271 | 木 | 木 | 高い木には風があたる |
| 271 | 擂粉木 | 擂粉木 | 擂粉木の大きな奴を |
| 272 | キンカン | 金柑 | 金柑は潰れるに |
| 272 | キンカン | 金柑 | 金柑とも薬罐とも |
| 273 | 椽側 | 椽側 | 椽側へ出て午睡をして |
| 273 | 木戸 | 木戸 | 木戸から廻って |
| 276 | 樹 | 樹 | 樹下石上を宿としなくとも |
| 277 | 擂粉木 | 擂粉木 | 擂粉木の大きな奴を |
| 277 | 擂粉木 | 擂粉木 | 擂粉木のあとに |
| 278 | 擂粉木 | 擂粉木 | 擂粉木が団子に |
| 278 | 擂粉木 | 擂粉木 | 擂粉木をやっと |
| 278 | 擂粉木 | 擂粉木 | 擂粉木の所有者に |
| 279 | キリ | 桐 | 桐の下葉を |
| 279 | 葉 | 葉 | 桐の下葉を |
| 280 | 椽側 | 椽側 | 椽側の前まで |
| 280 | ヤナギ | 柳 | 柳の下には必ず鰌がいる |
| 281 | 木戸 | 木戸 | 木戸口から庭中に |
| 285 | バラ | 薔薇 | 薔薇の水で |
| 289 | イチジク | 無花果 | 無花果を食うのを |
| 298 | ヒノキ | 檜 | 向に檜があるだろう |
| 303 | 椽側 | 椽側 | 椽側から書斎の入口まで |
| 309 | ヤナギ | 柳 | だいぶ柳の虫や赤蛙の |
| 317 | 椽側 | 椽側 | 椽側へ出て |
| 328 | マツ | 松 | あの松の木へカツレツが |
| 328 | マツ | 松 | 隠居の居る庭先の松の木を割いてしまった |
| 344 | 炭 | 炭 | 中から堅炭の |
| 344 | 炭 | 炭 | 炭の粉で真黒くなった |
| 350 | マツ | 松 | 鼻づらを松の木へ |
| 351 | ケヤキ | 欅 | この代物は欅か |
| 351 | 如輪木 | 如輪木 | 欅の如輪木か |
| 351 | ケヤキ | 欅 | 欅の如輪木か |
| 352 | サクラ | 桜 | 桜か桐か |
| 352 | キリ | 桐 | 桜か桐か |
| 357 | 算盤珠 | 算盤珠 | 算盤珠の様に |
| 391 | 木 | 老木 | 公園内の老木は森々として |
| 391 | 樹 | 樹 | 樹の茂った |
| 391 | 森々 | 森々 | 公園内の老木は森々として |
| 392 | スギ | 杉 | 老杉の葉を悉く振い落す様な勢で |
| 409 | ナツミカン | 夏蜜柑 | 夏蜜柑の様に |
| 409 | 梅干 | 梅干 | 中心から梅干が |
| 416 | カキ | 柿 | 甘干の柿を一つ食って |
| 416 | カキ | 柿 | 甘干の柿を一つ食って |
| 416 | カキ | 柿 | 柿はいいがそれから |
| 416 | 渋柿 | 渋柿 | 渋柿の甘干を |
| 416 | 渋柿 | 渋柿 | 渋柿の皮を剥いて |
| 417 | カキ | 柿 | 柿を食ってはもぐり |
| 417 | カキ | 柿 | 柿ばかり食ってて |
| 417 | カキ | 柿 | 又柿を食ったのかい |
| 419 | 木 | 木の葉 | 木の葉で路が一杯です |
| 419 | 森 | 森 | 東嶺寺の森が |
| 419 | 葉 | 落葉 | 折柄柿落葉の時節で |
| 419 | カキ | 柿 | 折柄柿落葉の時節で |
| 419 | 森 | 森 | 森から上は |
| 423 | ヤナギ | 枯柳 | 県庁の前で枯柳の数を勘定して |
| 429 | ムクゲ | むくげ | 丁度木槿垣を |
| 435 | 葉 | 落葉 | 星月夜に柿落葉 |
| 435 | カキ | 柿 | 星月夜に柿落葉 |
| 435 | カキ | 柿 | 甘干しの柿はないぜ |
| 436 | クス | 樟脳 | 樟脳を採る |
| 436 | マツ | 赤松 | 赤松の間から |
| 436 | クス | 楠 | 楠ばかりだ |
| 438 | 森 | 森 | 歌を森の中でうたってるところは |
| 478 | ヤナギ | 柳 | むっとして弁じましたる柳かな |
| 478 | ヤナギ | 柳 | むっとして戻れば庭に柳かな |
 中川木材産業のビジネスPR その18 (公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )
中川木材産業のビジネスPR その18 (公開2018.8.1 更新2019年11月11日 )