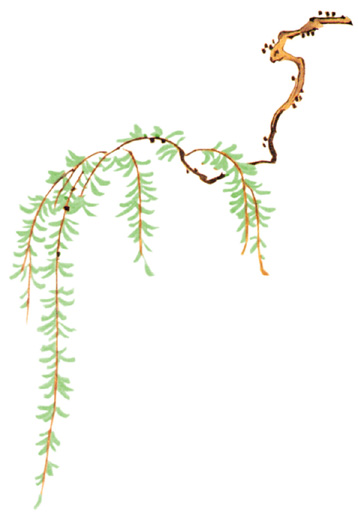ヤナギ
解説
ヤナギ科。日本に分布する。ヤナギとは、ヤナギ属に属する樹木の総称である。楊柳と表されるように、
ヤナギには楊の字もあてられるが、 中国では、シダレヤナギに代表されるヤナギ科ヤナギ属のものを柳、
ヤナギ科ハコヤナギ属ものを楊と、区別して使われことが多い。
ハコヤナギ属のヤナギとは、ドロノキ・ヤマナラシなど、いわゆるポプラの仲間をさす。楊柳ともに湿地を好
む落葉性の高木あるいは低木である。
ネコヤナギは川べりに生える落葉低木で、雌花の白い綿毛がネコを思わせることから、この名がつけられた。
コリヤナギの名は、その枝が今は 懐かしい「柳行李」の材料であったためである。
奈良の大仏殿がある東大寺の参道にはアカメヤナギ(フリソデヤナギ)の巨樹があり、奈良市の保存樹木となっています。
ヤナギ類は、世界で300種
以上、わが国でも30種以上にも及ぶ。しかしおおかたの人がまず 連想するのはシダレヤナギであるだろう。文学小説などではほとんどの場合シダレヤナギを指している。
文学
ヤナギを取り上げた小説とその数
ヤナギを取り上げた小説の素敵な文章
- 森鴎外の「雁」
- 微かに揺れている柳の糸、その向うの池一面に茂っている蓮の葉とが見える。(46頁)
- 夏目漱石の「吾輩は猫である 」
- 「むっとして弁じましたる柳かな、かね」と迷亭はあいかわらず飄然たる事を云う。(86頁)
- 尾崎紅葉の「金色夜叉 」
- 弱りし心は雨の柳の、漸く風に揺れたる勇を作して、(515頁)
- 島崎藤村の「桜の実の熟する時 」
- 青い柳の葉を心ゆくばかり嗅いだ。(68頁)
- 泉鏡花の「国貞えがく」
- 門の目印の柳と共に、枝垂れたようになって、折から森閑と風もない。(116頁)
- 永井荷風の「ふらんす物語 橡の落葉」
- 水の中(うち)見よりは柳の大樹生じて、道の上にまで、その長き枝を曳きたり。(280頁)
- 岡本かの子の「食魔」
- 堤の芽出し柳の煙れる梢に春なかばの空は晴れみ曇りみしている。(231頁)
- 宮沢賢治の「楊の木」
- けれどもいまでもまだ私には、楊の木に鳥を吸い込む力があると思えて仕方ないのです。(411頁)
- 川端康成の「古都」
- ほんとうにしだれ柳である。みどりの枝が、地につきそうに垂れて、いかにもやさしい。(52頁)
- 林芙美子の「放浪記」
- 所詮、私と云う女はあまのじゃくかも知れないのだ。柳は柳。風は風。(242頁)
- 井上靖の「天平の甍」
- 早春の陽を浴びて伊水(いすい) の水は温(ぬる)み、河畔の柳は生暖かい風にゆったりと揺れ動いていた。(53頁)
- 三島由紀夫の「金閣寺」
- 大そう聡明な一本の大きな柳が、濡れそぼった葉を重たげに垂らし、みずからに霧に揺られながら、現れたりした。(232頁)
- 宮尾登美子の「寒椿」
- 年も二十一の盛りとあって匂い立つわほどのあでやかさ、柳が歩めば花がもの云う、などと譬える人もあって、(291頁)
- 藤沢周平の「闇の穴」
- 柳の新葉が一せいに風にひるがえり、まぶしいほど目を弾(はじい)た。(112頁)
樹形

富田林市内
ヤナギの巨樹

奈良公園(東大寺のアカメヤナギ)のアカメヤナギ

ウィーン植物園 2015年9月26日

ドロノキ旭川 永山開拓年保護樹 1998年8月8日