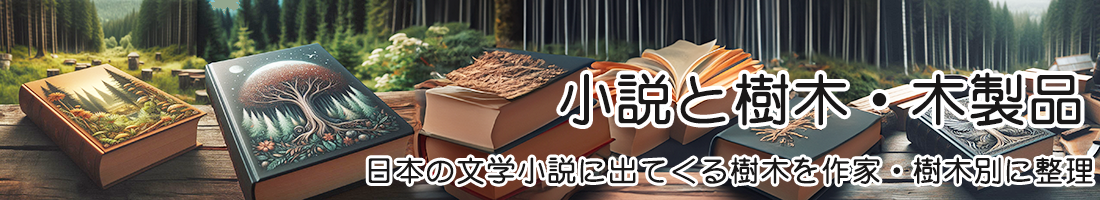| 95 |
棹 |
棹 |
いずれその棹(さお)に星条旗が付けられるような |
| 103 |
柵 |
柵 |
柵は低かった。 |
| 103 |
柵 |
柵 |
柵と道路の間には五尺がかりの溝があった。 |
| 107 |
ポプラ |
ポプラ |
空に亭々(ていてい)と伸びるポプラの木立がある。 |
| 107 |
木立 |
木立 |
空に亭々(ていてい)と伸びるポプラの木立がある。 |
| 107 |
葉 |
葉 |
葉の茂っているときもいいし、 |
| 107 |
板 |
板の間 |
天井から落ちた滴で板の間に氷塊ができる。 |
| 115 |
葉 |
葉 |
その葉の上にかかった夕月は私の気持ちをなごませた。 |
| 115 |
ポプラ |
ポプラ |
最後に丘の上のポプラが見えなくなる。 |
| 116 |
木 |
木の蔭 |
家の中や木の蔭は涼しかった。 |
| 121 |
木 |
木 |
女たちのためにはなるべく木の茂った蔭がえらばれた。 |
| 125 |
ハゼノキ |
櫨 |
道はそれに沿って櫨(はぜ)の気の多い平野に入る。 |
| 125 |
木 |
櫨の木 |
道はそれに沿って櫨(はぜ)の木の多い平野に入る。 |
| 125 |
ハゼノキ |
櫨 |
高い櫨の樹の上にも飛んでいた。 |
| 125 |
樹 |
櫨の樹 |
高い櫨の樹の上にも飛んでいた。 |
| 128 |
ハゼノキ |
櫨 |
櫨の立木がんならぶ美しい田園である。 |
| 128 |
立木 |
立木 |
櫨の立木がんならぶ美しい田園である。 |
| 140 |
木 |
木 |
ぼつぼつ建っているバラックの木の新しさだけが眼をむいていた。 |
| 141 |
櫺子 |
櫺子 |
畳の上に櫺子(れんじ)で囲った帳場があり、 |
| 145 |
木槌 |
木槌 |
藁を木槌で叩いて中の芯を抜き、 |
| 148 |
松林 |
松林 |
トンネルを過ぎると松林があって、 |
| 148 |
板壁 |
板壁 |
小屋は、板壁の隙間から風が入っていた。 |
| 150 |
板壁 |
板壁 |
机を板壁に嵌(はま)ったガラス戸の下に置き、 |
| 153 |
木製 |
木製 |
おどろいたことに木製の大きな「機械」が櫓(やぐら)のように |
| 153 |
櫓 |
櫓 |
この櫓が針金の巻取機械であった。 |
| 153 |
木製 |
木製 |
頼もしげに木製機械に這いのぼっている男 |
| 153 |
大工 |
大工 |
彼が設計して大工にでも作らせたらしいその櫓を眺めて |
| 153 |
櫓 |
櫓 |
彼が設計して大工にでも作らせたらしいその櫓を眺めて |
| 153 |
櫓 |
櫓 |
おどろいたことに木製の大きな「機械」が櫓(やぐら)のように |
| 155 |
木製 |
木製 |
木製の機械は廃屋の工場に偉容を誇ったまま |
| 155 |
大工 |
大工 |
何度も大工に作り直させてはやったもんですから、 |
| 159 |
柱 |
柱 |
外陣の柱や欄間にも剥落(はくらく)の跡がひどく、 |
| 159 |
欄間 |
欄間 |
外陣の柱や欄間にも剥落(はくらく)の跡がひどく、 |
| 159 |
新緑 |
新緑 |
渓谷は新緑のなかで美しかった。 |
| 162 |
板 |
板 |
半截(はんさい)ぐらいの画用紙を板に水貼りして、 |
| 163 |
板 |
板 |
陳列用の大きな板に色を塗る厄介さは想像以上で、 |
| 168 |
松林 |
松林 |
沖を眺めたり、松林の間を歩き回ったりした。 |
| 172 |
指物大工 |
指物大工 |
大分県の田舎で指物大工をしていて、 |
| 179 |
木履 |
木履 |
神主さんのはいている木履(ぼくり)のようだと評した。 |
| 8 |
木 |
杉の木 |
今では日南町と名前が変わっている。山に杉の木が多い。 |
| 8 |
カキ |
柿の実 |
柿の実のなった梢の下の径を歩いた。 |
| 8 |
実 |
柿の実 |
柿の実のなった梢の下の径を歩いた。 |
| 8 |
梢 |
梢 |
柿の実のなった梢の下の径を歩いた。 |
| 13 |
格子戸 |
格子戸 |
壊れかかった格子戸を手荒く閉めて行った |
| 15 |
杭 |
杭 |
海に打った杭の上に載っていた。 |
| 16 |
森 |
森 |
山を背に鬱蒼とした森に囲まれ、 |
| 16 |
モモ |
森 |
手首に森桃の刺青があった。 |
| 20 |
タイマツ |
タイマツ |
そのタイマツの火でまるで山の下のほうがクワジみたいになった」 |
| 21 |
船大工 |
船大工 |
船大工、漁師といった商売だつた。 |
| 24 |
柾目 |
柾目 |
ぞろりとした絹物に着更(きがえ)え、柾目の下駄をはき、 |
| 26 |
木賃宿 |
木賃宿 |
恥ずかしい思いでついて行くと、そこが木賃宿であった。 |
| 26 |
ナツメ |
棗の実 |
都会の果物屋に棗の実があまり見られなくなった。 |
| 26 |
実 |
棗の実 |
都会の果物屋に棗の実があまり見られなくなった。 |
| 26 |
ナツメ |
棗 |
高級果物のなかでは、棗などは見向きされなくなったのであろう。 |
| 26 |
果実 |
果実 |
いくらか蒼味(あおみ)のかかった果実が好きであろう。 |
| 26 |
木賃宿 |
木賃宿 |
その木賃宿では、殺風景な広い座敷に、 |
| 26 |
ナツメ |
棗の実 |
買ってきた棗の実を私に食わせた。 |
| 26 |
棗の実 |
棗の棗の実 |
買ってきた棗の実を私に食わせた。 |
| 29 |
木造 |
木造建 |
終点近くに木造建の古い教会があった。 |
| 29 |
板 |
板囲い |
路地の奥に包まれた板囲いのバラックだった。 |
| 29 |
板 |
板 |
間の仕切りも板で区切られていた。 |
| 33 |
木橋 |
木橋 |
裏町のドブ川にかかった小さな木橋がいくつもあった。 |
| 33 |
板塀 |
板塀 |
路地の突き当たりの黒い板塀の家に |
| 35 |
森 |
森 |
森の中に小さな祠かせあって、 |
| 35 |
マツ |
松の木 |
路傍の松の木の下にメリケン粉の袋の布で |
| 35 |
木 |
松の木 |
路傍の松の木の下にメリケン粉の袋の布で |
| 42 |
木賃宿 |
木賃宿 |
私の父親の木賃宿の思い出につながった。 |
| 50 |
板の間 |
板の間 |
ある冬の日、板の間に座って、かじかむ手で版下を |
| 53 |
木箱 |
木箱 |
剥(は)げた木箱の官食を口にいれたが、 |
| 53 |
板 |
板 |
便所には二枚の板が四角い壺に差し渡されてあるだけで、 |
| 7 |
スギ |
杉の木 |
今では日南町と名前が変わっている。山に杉の木が多い。 |
| 54 |
サクラ |
桜 |
出てきたときは桜が咲いていた。 |
| 56 |
ウメ |
梅 |
私は楕円形や、梅、桜といったかたちが、 |
| 56 |
サクラ |
桜 |
私は楕円形や、梅、桜といったかたちが、 |
| 58 |
指物 |
指物大工 |
元は田舎で指物大工をしていたが、 |
| 58 |
大工 |
指物大工 |
元は田舎で指物大工をしていたが、 |
| 64 |
シタン |
紫檀 |
十二畳の座敷の真中に紫檀の机を置き、 |
| 65 |
マツ |
松の木立 |
寒い風にそよぐ松の木立があった。 |
| 65 |
木立 |
松の木立 |
寒い風にそよぐ松の木立があった。 |
| 66 |
柾目 |
柾目 |
柾目の下駄をはいて、往来を風を切って |
| 66 |
木造 |
木造 |
木造小舎での生活だった。 |
| 70 |
白木 |
白木 |
大八車の上に白木の棺を載せ、 |
| 72 |
大樹 |
大樹 |
銀杏の大樹があって、その向こうは遠賀川になっていた。 |
| 72 |
サクラ |
桜 |
桜が咲くと、その姉は妹を私につけて |
| 88 |
落葉 |
落葉 |
風に散ってゆく落葉のようだった。 |
| 95 |
木製 |
木製 |
巻脚絆(ぎやはん)をつけて木製の銃剣を振る気にはなれなかった。 |