
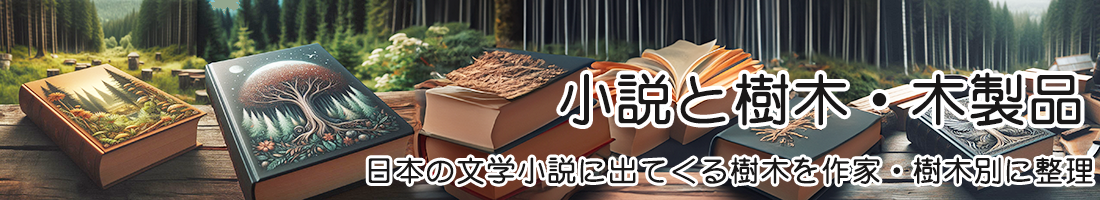
| ページ | 元樹種 | 掲載樹種 | 掲載言葉 |
|---|---|---|---|
| 9 | 芸妓子方屋 | 芸妓子方屋 | 浦戸町の芸妓子方屋の松崎には |
| 9 | 葉 | 葉 | 堅い葉のあいだを掻き分けて |
| 9 | ツバキ | 椿 | 椿は肉厚の白や斑の八重や |
| 9 | 木 | 木 | 日かげの木とでは |
| 9 | ツバキ | やぶつばき | 素っ気ない一重の藪椿など |
| 9 | ツバキ | 椿 | 椿、ないかないか |
| 9 | 花 | 花 | 花、ないかないか |
| 9 | ツバキ | 椿 | 椿はぽたりと首からもげると云われるが必ずしも全部がそうではなく |
| 9 | 葉裏 | 葉裏 | 葉裏にうつむいて |
| 9 | ツバキ | 椿 | とくに椿は着物ばかりでなく |
| 9 | ツバキ | 椿 | 椿の木が六本植えられていた |
| 21 | 丸太 | 丸太ン棒 | 躰は相変わらずの丸太ン棒のまま |
| 32 | 桃割 | 桃割 | 初めて結った桃割れを |
| 32 | ツバキ | 椿 | 落ちていた椿の花を |
| 38 | 板 | 板 | 鉋を掛けた一枚板のように |
| 38 | 植木 | 植木 | 隅の植木鉢のかげで |
| 51 | ナシ | 梨 | 便りを出しても梨の礫ゆえ |
| 67 | 懇ロ | 懇ろ | 女事務員と懇(ねんご)ろになった事が |
| 75 | ツバキ | 椿 | 椿の木があったらなおよい |
| 75 | 板塀 | 板塀 | 形ばかりの板塀に |
| 76 | 板塀 | 板塀 | こちらの板塀の隙間から |
| 78 | 吊シ柿 | 吊し柿 | 自分こそ吊し柿 |
| 99 | ツバキ | 椿 | 六本の椿の木を瞼の裏に |
| 106 | 木 | 木立 | 車の上ってゆく木立の間からは |
| 107 | 木 | 木立 | 次の木立に入り |
| 108 | ヤマモモ | 楊うめ | 楊梅の木のある松崎の墓所に |
| 108 | 木 | 木洩れ日 | 楊梅の大木の木洩れ日を浴び乍ら |
| 108 | ヤマモモ | 楊うめの大木 | 楊梅の大木の木洩れ日を浴び乍ら |
| 109 | 木仏 | 木仏 | 木仏金仏でもないつもりだが |
| 112 | ヤナギ | 柳 | 播磨屋橋脇の柳の下に立って |
| 133 | 木 | 木の床 | ホームの木の床に蔓った苔の色は |
| 134 | 板壁 | 板壁 | この板壁が使われ |
| 134 | マツ | 松原 | 最も海に近い松原のなかにあった |
| 134 | 板 | 板 | 板囲いの外側には |
| 135 | マツ | 松 | 松の根をいくつか飛び越せば |
| 135 | 根 | 根 | 松の根をいくつか飛び越せば |
| 135 | 板 | 板 | 板囲いのなかの狭い家には |
| 155 | ツバキ | 椿 | 無闇に椿の葉っぱを毟ったりする |
| 155 | 葉 | 葉っぱ | 無闇に椿の葉っぱを毟ったりする |
| 156 | 花 | 花びら | 肉厚の花びらをむしゃむしゃと食べたところ、女中たちも一緒になって |
| 163 | 撞木 | 撞木 | 前差し後差し撞木差しに寝た情景も |
| 164 | 木 | 木 | 木の家というのは一軒だって見つからぬ |
| 165 | 木 | 木 | 木の家も見えぬ町の姿に |
| 167 | ヤナギ | 柳 | 民江の態度を柳に風と受け流している |
| 175 | サクラ | 桜 | 同期の桜のせいか |
| 179 | ミカン | 蜜柑箱 | 部屋の隅の蜜柑箱の上には |
| 180 | 根 | 根 | 松の根を踏んで |
| 180 | マツ | 松 | 松の根を踏んで |
| 181 | 板小屋 | 板小屋 | 板小屋で息を引き取ったと |
| 182 | 板小屋 | 板小屋 | 板小屋のなかの板敷に |
| 182 | 板敷 | 板敷 | 板小屋のなかの板敷に |
| 182 | マツ | 松 | 松原を鳴らしてゆく潮風や |
| 189 | 韮 | 韮 | 見どころとてなし韮の花 |
| 189 | 韮 | 韮 | 韮の花とて蝶集む |
| 194 | ヤナギ | 柳 | 好いた水仙好かれた柳 |
| 201 | 木阿弥 | 木阿弥 | すべて元の木阿弥で |
| 204 | マツ | 松 | 松原の松の匂い |
| 206 | 板小屋 | 板小屋 | 板小屋で五年間も病んだ |
| 210 | サンザシ | さんざし | 山査子の赤い実を |
| 210 | 焼クリ | 焼栗 | くーりー焼栗っ、もええよ |
| 210 | ミカン | 蜜柑 | 凍り蜜柑をストーブで焼いて |
| 210 | サンザシ | タンフールー(糖葫芦) | 赤い実を飴で固めたタンフールー |
| 210 | 実 | 実 | 山査子の赤い実を |
| 212 | カキ | つるし柿 | 味は大和のつるし柿 |
| 214 | 板小屋 | 板小屋 | 板小屋に一人暮らしていたが |
| 218 | マツ | まつ林 | 松林を縫って吹き抜け |
| 218 | マツ | 松原 | 松原の中に並んだ |
| 219 | サクラ | 牡丹さくら | 牡丹桜が重そうに |
| 241 | 若葉 | 若葉 | 銀杏の若葉の頃が |
| 241 | イチョウ | 銀杏 | 銀杏の若葉の頃が |
| 256 | 上框 | 上り框 | 上り框に斜めに腰かけた |
| 256 | サクラ | 桜 | 白い桜の花を背負っていた |
| 263 | サクラ | 桜 | 桜の大木の下に |
| 263 | 木 | 大木 | 桜の大木の下に |
| 263 | サクラ | 桜 | 桜の花の光景を |
| 263 | 落花 | 落花 | 落花を浴びながら突っ立っている |
| 265 | 板 | どぶ板 | どぶ板を跨いで |
| 273 | マツ | まつ林 | 松林のなかを抜けて |
| 275 | 薪 | 薪 | 製材所の挽き落しの薪を |
| 275 | 製材所 | 製材所 | 製材所の挽き落しの薪を |
| 277 | 薪 | 薪 | 薪を幾百束幾千束売っても |
| 279 | ツバキ | 椿 | 椿のある長い敷石の道を |
| 291 | ヤナギ | 柳 | 柳が歩めば花がもの云う |
| 291 | 若葉 | 若葉 | 若葉の燃えるような勤めぶりだったと |
| 292 | 木 | 木の葉 | 石の上の木の葉を拾うたら |
| 298 | 大工 | 大工 | 大工の仕事はひきも切らずあり |
| 303 | 熟柿 | 熟柿 | 熟柿が好きだったから |
| 303 | 葉 | 葉 | 唇許からは黄になった萩の葉のような |
| 303 | ハギ | 萩 | 唇許からは黄になった萩の葉のような |
| 309 | マツ | 松の花 | あら、松の花 |
| 309 | マツ | 松 | 松の花が目についたのは |
| 309 | 花粉 | 花粉 | その花粉を払い |
| 310 | 花粉 | 花粉 | 黄の花粉を目に灼きつけたことで |
| 311 | 松明 | 松明 | 松明を半分残しておき |
| 311 | 松明 | 松明 | その松明で飯を炊くと |
| 312 | 梢 | 梢 | 赤松の梢を暫く仰ぎ |
| 312 | アカマツ | 赤松 | 赤松の梢を暫く仰ぎ |
| 313 | アカマツ | 赤松 | 赤松の下に佇っていたとき |
| 313 | マツ | 松の花 | さっき見た松の花の |
| 313 | 疎林 | 疎林 | 疎林のあいだから |
| 313 | 蕾 | 蕾 | 花の蕾のかたちに |
| 314 | コウゾ | こうぞ | 楮を五貫 |
| 314 | 筏師 | 筏師 | 筏師の父親が |
| 315 | 薪 | 薪 | 薪から米まで買って |
| 334 | サルスベリ | 百日紅 | 百日紅の花が炎と紛う |
| 368 | 懇ロ | 懇ろ | 懇ろに頼んであり |
| 372 | ケヤキ | 欅 | 欅の葉色や |
| 372 | 葉 | 葉 | 欅の葉色や |
| 372 | ツバキ | 椿 | 植えられた椿 |
| 372 | サルスベリ | 百日紅 | 百日紅の花模様であったり |