

ベイマツは学名を Pseudotsuga menziesii といい、英語では Douglas-fir、Oregon Pine、Columbian Pine などと呼ばれます。和名では米松とされますが、植物学的にはマツ属ではなく、トガサワラ属に分類されます。北米の太平洋岸、カナダ・ブリティッシュコロンビア州南部から米国のワシントン州、オレゴン州、カリフォルニア州、さらにメキシコ北部まで広く分布しており、原産地では地域や成長条件によって年輪幅や色調、比重に大きな違いが見られます。これは構造材としては許容されますが、意匠材としては選別が重要となります。また、19世紀後半からヨーロッパやニュージーランド、南米チリなど温帯地域でも造林が進み、英国やアイルランドでは成長が良く高木が得られることから、林業樹種として定着しています。
この樹木は通直な幹を持つ常緑高木で、原産地では樹高50〜60m、稀に90mを超え、幹径は1〜2m、まれに4mに達することもあります。原産地では500年以上の寿命を持つ個体も珍しくありません。成長速度は早く、特にアイルランドなど温暖湿潤の気候ではヨーロッパの他地域よりも太く高く育ちます。こうした大径・長尺材が得られる点が建築構造材としての最大の魅力であり、現代建築では長スパンを可能にする集成材やCLTのラミナ材として高く評価されています。
ベイマツの木材は心材と辺材の色の差が明瞭で、心材は黄色や黄褐色、赤褐色など成長条件によって変化します。年輪幅が狭く比重が低いものはイエローファー、年輪幅が広く比重が高いものはレッドファーと呼ばれ、北米市場でも区別されています。年輪ははっきりしており、材肌は粗く、平均気乾比重は0.55と針葉樹材の中ではやや重硬です。木理は通直で、やや脂っぽい手触りを持ちますが、樹脂道を含むため乾燥後もヤニが滲み出すことがあり、意匠仕上げ面では十分な乾燥と選別が必要です。強度性能は曲げ・圧縮とも高く、寸法安定性や加工性にも優れ、釘着性・接着性も良好です。湿潤環境では耐久性にやや不安があり、防腐処理を施すことで長期利用が可能になります。
乾燥は比較的早く狂いも少ないため、大断面材や長尺材でも加工が容易です。手加工や機械加工もスムーズで、構造材から合板、集成材まで幅広く対応できます。柾目材は表面が美しく、床板やデッキ材にも適していますが、板目材はささくれが生じやすいため、用途に応じた木取りが求められます。特に外装材や屋外デッキとして使う場合は、寸法安定性と仕上がりの両立を考慮して選材されます。
原産地の北米では、ベイマツは梁、桁、柱などの構造材として最も重要な針葉樹であり、大スパンの屋根トラスや港湾施設、橋梁材にも使用されます。耐荷重性の高さと長材が得られる特性から、鉄道の枕木、化学薬品槽やタンク、集成梁やCLTパネル、そして構造用合板の原料としても世界的に重要です。日本の住宅においても桁材の多くが米松で、特に長尺材の供給源として欠かせません。家具や建具には主に内部構造や下地用途で使われますが、仕上げ面に使用する場合はヤニの処理が課題となります。
耐朽性は針葉樹材として中程度で、屋外や地中に接する使用では防腐処理が推奨されます。特に湿潤気候や高温環境下では白蟻被害を受けやすく、日本やアジア圏では防蟻処理が不可欠です。北米やヨーロッパの一部では、港湾構造物や屋外構造物に使用する際に加圧注入処理(CCAなど)を施し、耐用年数を大幅に延ばしています。こうした処理を行うことで、海水に接する用途でも長期間使用できる優れた構造材となります。
日本におけるベイマツの輸入は明治時代に始まり、当時は「メリケンマツ」と呼ばれていました。戦後の住宅需要拡大に伴い輸入量が急増し、現在では北米材輸入の中で最大シェアを占める樹種の一つとなっています。国内での植林は病害のため成林が難しく、ほぼ輸入材に依存しています。近年では北米西岸での持続可能な森林経営が進み、FSCやSFIなど国際的な森林認証を取得したベイマツも多く流通しており、環境配慮型建築の材料としても注目を集めています。
1970年の万博では日本のパビリオンが木材を使わないのに比べ、海外のパビリオンでは多用していました。米国、カナダ、ニュージランドなどの当時の先進国やタンザニア、フィリピン、チェコ、ブルガリア、タイ、ビルマ、シンガポール、マレーシアなどの国で木材が多用されていました。特に注目を浴びたのがカナダ・ブリティシュコロンビア館です。
ベイマツの丸太をそのまま利用したもので高さ50メートルもありました。またカナダ館も完全な木造建築で建築面積1000坪以上の巨大なピラミッド形で表面には鏡が貼り付けてありましたが、ベイマツの集成材で作られていました。
2025年の関西万博では、多くのパビリオンが木材を多用するようになりました。そんな中でベイマツを利用しているのがアイルランド館です。人気のあるパビリオンで入館は最難関となっています。同国のベイマツは19世紀後半〜20世紀初頭に北米から導入、木材生産や防風林・景観用樹種として利用されてきました。以下にアイルランド産と米国産の比較を掲載します。
| 項目 | アイルランド産 | 北米産(原産地) |
|---|---|---|
| 平均樹高(成木) | 45〜55 m | 60〜75 m |
| 平均胸高直径(成木) | 0.8〜1.2 m | 1.0〜2.0 m |
| 気乾比重 | 0.46 | 0.50 |
| 曲げ強度(MPa) | 88 | 90 |
| 圧縮強度(MPa) | 47 | 49 |
| 耐朽性 | 中程度(屋外使用では防腐処理推奨) | 中〜やや高(乾燥地産は耐久性やや高い) |
| 色調(心材) | 淡紅褐色 | 淡紅褐色〜濃赤褐色 |
| 年輪幅 | 広め(成長が速いため) | やや狭め(成長やや遅い地域も多い) |












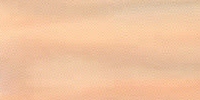
 中川木材産業のオリジナル推し商品
中川木材産業のオリジナル推し商品