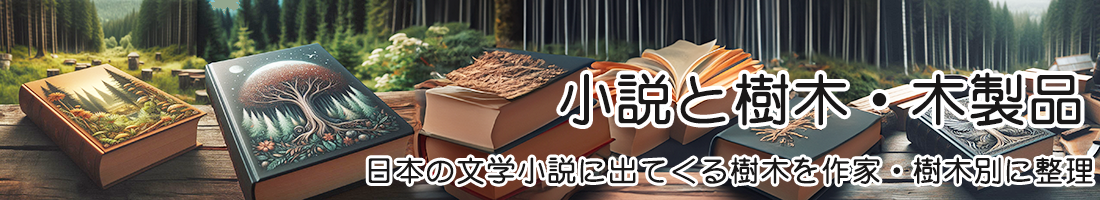| マツ |
異端者の悲しみ |
106 |
松 |
松の葉越しに女は |
| ウメ |
異端者の悲しみ |
164 |
梅 |
降りつづいた入梅の空が |
| ウメ |
異端者の悲しみ |
166 |
梅 |
あの容態じゃあ入梅明けまで |
| サクラ |
吉野葛 |
13 |
桜 |
春の桜、秋の紅葉もみじ、それらを取り取りに生かして使える。 |
| コウゾ |
吉野葛 |
15 |
こうぞ |
吉野川の水に楮の繊維を晒しては、手ずきの紙を製するのである。 |
| カキ |
吉野葛 |
22 |
柿 |
八百屋の店先に並べてある柿が殊に綺麗であった。 |
| カキ |
吉野葛 |
22 |
柿 |
キザ柿、御所柿、美濃柿、いろいろな形の粒が |
| サクラ |
吉野葛 |
23 |
桜 |
「君、妹背山の次には義経千本桜があるんだよ」 |
| ハゼ |
吉野葛 |
26 |
櫨 |
櫨、山漆にど |
| クヌギ |
吉野葛 |
26 |
櫟 |
われわれはしばしば櫟林の中に這入って、一面に散り敷く落葉の上をかさかさ音を立てながら行った。 |
| カエデ |
吉野葛 |
26 |
楓 |
この辺へん、楓が割合いに少く、かつひと所にかたまっていないけれども、紅葉は今が真まっ盛さかりで、 |
| クワ |
吉野葛 |
29 |
桑 |
桑が丈高く |
| クワ |
吉野葛 |
29 |
桑の葉 |
桑の葉の |
| クワ |
吉野葛 |
29 |
桑畑 |
桑畑の中 |
| ウメ |
吉野葛 |
33 |
梅鉢 |
梅鉢もう一つの方は梅鉢の紋で、 |
| キリ |
吉野葛 |
33 |
桐 |
ただ胴ばかりが桐の箱に収まっていた。 |
| カキ |
吉野葛 |
35 |
柿 |
市中に売っている樽柿などは、 |
| カキ |
吉野葛 |
35 |
柿 |
ずくしはけだし熟柿であろう。 |
| カキ |
吉野葛 |
35 |
柿 |
ずくしを作るには皮の厚い美濃柿に限る。 |
| カキ |
吉野葛 |
35 |
柿 |
円錐形の、尻の尖った大きな柿であるが、真っ赤に熟し切って半透明になった果実は、あたかもゴムの袋ふくろのごとく膨でぶくぶくしながら、日に透かすと琅(ろう)かんの珠のように美しい。 |
| カキ |
吉野葛 |
35 |
柿 |
盆ぼんに盛った柿の実、灰の這入っていない空の火入れを添えて出した。 |
| カキ |
吉野葛 |
35 |
柿 |
どろどろに熟れた柿の実を、 |
| マンゴー |
吉野葛 |
36 |
あんもらか |
思うに仏典中にある庵摩羅果(あんもらか)もこれほど美味 |
| カキ |
吉野葛 |
36 |
柿 |
そとの柿だと、 |
| サクラ |
吉野葛 |
37 |
桜 |
千本桜なら下市だろう、あそこの釣瓶鮨屋と云うのは聞いているが、―――」 |
| サクラ |
吉野葛 |
50 |
桜 |
が、千本桜の道行になると、 |
| マツ |
吉野葛 |
67 |
松 |
松林の中に |
| マツ |
吉野葛 |
67 |
松 |
磯馴松 |
| ウメ |
吉野葛 |
68 |
梅 |
八重梅 |
| カシワ |
吉野葛 |
68 |
柏 |
「柏葉」の下に五色の雲と天人の姿が透すいて見える。 |
| マツ |
吉野葛 |
70 |
松 |
松竹梅 |
| シイ |
吉野葛 |
71 |
椎の木 |
祠のうしろにある椎の木の蔭にむかし狐が棲んでいた穴が残っているばかりで、 |
| クワ |
吉野葛 |
75 |
桑 |
樫、櫟、桑 |
| カシ |
吉野葛 |
75 |
樫 |
樫、櫟、桑 |
| クヌギ |
吉野葛 |
75 |
櫟 |
炉には樫、櫟、桑などをくべたが、桑が一番火の保ちがよく、熱も柔らかだと云うので、 |
| クワ |
吉野葛 |
75 |
桑 |
樫、櫟、桑 |
| クワ |
吉野葛 |
75 |
桑 |
桑が一番火の保がよく、熱も柔らか |
| スギ |
吉野葛 |
77 |
杉 |
木深い杉林の中に |
| ツバキ |
吉野葛 |
78 |
椿 |
刻煙草を煙管の代りに椿の葉に巻いて口に咬え、嶮い道を楽に越えながら、 |
| ツツジ |
細雪 |
5 |
ヒラドツツジ |
庭の平戸の花 |
| シラカンバ |
細雪 |
5 |
白樺 |
白樺の椅子 |
| クリ |
細雪 |
6 |
栗 |
栗の樹に栗が沢山実っていた |
| カエデ |
細雪 |
35 |
楓 |
楓の老樹の新緑を透かして |
| ザクロ |
細雪 |
35 |
遠柘榴 |
石榴が花を着けている |
| パンヤ |
細雪 |
40 |
パンヤ |
寝台用の藁布団の上にパンヤの敷布団を二枚重ね、 |
| ライラック |
細雪 |
55 |
ライラック |
ライラックと栴檀の樹の間 |
| センダン |
細雪 |
55 |
せんだん |
ライラックと栴檀の樹の間 |
| アオギリ |
細雪 |
64 |
青桐 |
青桐と栴檀の葉の隙間 |
| センダン |
細雪 |
64 |
栴檀 |
青桐と栴檀の葉の隙間 |
| マツ |
細雪 |
91 |
松 |
堤防の松を砂煙で汚していた |
| センダン |
細雪 |
94 |
センダン |
栴檀と青桐の葉はおびただしく繁って |
| クチナシ |
細雪 |
94 |
梔子 |
咲き残った梔子の花 |
| ツツジ |
細雪 |
94 |
つつじ |
霧島や平戸も散ってしまい |
| ライラック |
細雪 |
94 |
ライラック |
ライラックと小手毬が満開 |
| コデマリ |
細雪 |
94 |
こでまり |
ライラックと小手毬が満開 |
| サツマウツギ |
細雪 |
94 |
さつまうつぎ |
さつまうつぎや八重山吹はまだ咲いていなかった |
| ヤマブキ |
細雪 |
94 |
八重山吹 |
さつまうつぎや八重山吹はまだ咲いていなかった |
| アオギリ |
細雪 |
95 |
青桐 |
青桐の葉をガサガサと鳴らして、 |
| アオギリ |
細雪 |
95 |
あおぎり |
「アオギリギリですか」 |
| アオギリ |
細雪 |
95 |
青桐 |
青桐は枝を境界の向こう側へ差し出している |
| チョウジ |
細雪 |
137 |
丁子 |
「おや、何処かで丁子が匂におうてる。 |
| サクラ |
細雪 |
137 |
桜 |
「あーあ、まだ桜が咲くまでには一と月あるねんなあ、待ち遠やわ」 |
| マツ |
細雪 |
143 |
松 |
昔の面影を伝えている大木の松などが二三本取り入れてあり、 |
| コデマリ |
細雪 |
143 |
コデマリ |
白い細かい花をつけた小手毬こでまりが、 |
| サクラ |
細雪 |
143 |
桜 |
右の方の汀(みぎわ)には桜とライラックが咲いていた。 |
| ライラック |
細雪 |
143 |
ライラック |
右の方の汀(みぎわ)には桜とライラックが咲いていた。 |
| サクラ |
細雪 |
143 |
桜 |
桜は幸子が好きなので、たとい一本でも |
| ヤマブキ |
細雪 |
144 |
八重山吹 |
離れ座敷の袖垣(そでがき)のもとにある八重山吹の咲くのと同時ぐらいなので、 |
| アオギリ |
細雪 |
144 |
青桐 |
網に沿うた青桐の下の、午後の陽光がうらうらと照っている芝生の上に、 |
| ライラック |
細雪 |
144 |
ライラック |
いつも小手毬やライラックが散った後 |
| キリ |
細雪 |
144 |
桐 |
桐の紋のある襖 |
| コデマリ |
細雪 |
144 |
ライラック |
いつも小手毬やライラックが散った後、 |
| カリン |
細雪 |
144 |
かりん |
花梨の卓 |
| ライラック |
細雪 |
144 |
ライラック |
ライラックは今雪のように咲き満ち |
| サツマウツギ |
細雪 |
144 |
さつまうつぎ |
その「さつまうつぎ」の向うが、シュトルツ氏の裏庭との境界の金網になっていて、 |
| ウツギ |
細雪 |
144 |
うつぎ |
日本語では「さつまうつぎ」と云うところの卯木の一種であることを知ったが、 |
| ライラック |
細雪 |
144 |
ライラック |
ライラックの木の西に |
| センダン |
細雪 |
144 |
センダン |
まだ芽を出さない栴檀(せんだん)と青桐(あおぎり)があり、栴檀の南に、仏蘭西語で「セレンガ」と云う灌木の一種があった。 |
| サツマウツギ |
細雪 |
144 |
さつまうつぎ |
日本語では「さつまうつぎ」と云うところの卯木の一種であることを知ったが、 |
| アオギリ |
細雪 |
144 |
青桐 |
まだ芽を出さない栴檀(せんだん)と青桐(あおぎり)があり、栴檀の南に、仏蘭西語で「セレンガ」と云う灌木の一種があった。 |
| バイカウツギ |
細雪 |
144 |
セレンガ(ばいかうつぎ) |
まだ芽を出さない栴檀(せんだん)と青桐(あおぎり)があり、栴檀の南に、仏蘭西語で「セレンガ」と云う灌木の一種があった。 |
| センダン |
細雪 |
144 |
センダン |
まだ芽を出さない栴檀(せんだん)と青桐(あおぎり)があり、栴檀の南に、仏蘭西語で「セレンガ」と云う灌木の一種があった。 |
| サクラ |
細雪 |
146 |
桜 |
躊躇なく桜と答えるのであった。 |
| サクラ |
細雪 |
146 |
桜 |
桜の花に関する歌 |
| サクラ |
細雪 |
148 |
桜樹 |
桜樹の前に立ち止まって |
| サクラ |
細雪 |
148 |
枝垂桜 |
円山公園の枝垂桜 |
| サクラ |
細雪 |
149 |
桜 |
桜の樹の下に立って |
| サクラ |
細雪 |
149 |
桜 |
一本の桜の樹の下に |
| ツバキ |
細雪 |
149 |
椿 |
見事な椿の樹があって毎年真紅の花をつけることを覚えていて、必ずその垣根のもとへも立ち寄るのであった。 |
| サクラ |
細雪 |
150 |
桜 |
入り口のところにある桜 |
| サクラ |
細雪 |
150 |
桜 |
海外にまでその美を謳ていると云う名木の桜が、 |
| カシ |
細雪 |
151 |
樫 |
まだ軟かい芽を出したばかりの楓や樫があり、 |
| サクラ |
細雪 |
151 |
桜樹 |
桜樹の尽きたあたり |
| カエデ |
細雪 |
151 |
楓 |
まだ軟かい芽を出したばかりの楓や樫があり、 |
| アセビ |
細雪 |
151 |
あしび |
円く刈り込んだ馬酔木あしびがある。 |
| カリン |
細雪 |
152 |
かりん |
今は新緑にも早く、わずかに庭前の筧(かけひ)の傍にある花梨の莟つぼみが一つ綻ほころびかけているのを、 |
| サクラ |
細雪 |
152 |
桜 |
まだ厚咲きの桜には間があることが分っていたけれども、 |
| シラカンバ |
細雪 |
155 |
白樺 |
皮つきの白樺の丸太で作った椅子に掛けているのであったが、 |
| カシ |
細雪 |
155 |
樫 |
大明竹や樫の葉の生い繁った薄暗い方へもぐって行ってしまったので、 |
| ハギ |
細雪 |
163 |
白萩 |
一叢の白萩がしなだれている |
| フヨウ |
細雪 |
163 |
ふよう |
貧弱な芙蓉が咲いている |
| センダン |
細雪 |
164 |
センダン |
葉を繁らした栴檀と青桐とが暑苦しそうな枝ひろげ、 |
| モクセイ |
細雪 |
164 |
木犀 |
何処からか木犀の匂いが |
| マツ |
細雪 |
164 |
松 |
松の樹の多い |
| アオギリ |
細雪 |
164 |
青桐 |
葉を繁らした栴檀と青桐とが暑苦しそうな枝をひろげ、 |
| トガ |
細雪 |
169 |
とが |
やつやと拭ふき込んだ栂の柱が底光りをしていようと云う、 |
| アオギリ |
細雪 |
176 |
青桐 |
青桐の下へ駆けて行って |
| アオギリ |
細雪 |
176 |
青桐 |
青桐の幹 |
| サクラ |
細雪 |
181 |
桜 |
枝を差し出した一本の桜 |
| モクレン |
細雪 |
195 |
木蓮 |
白木蓮や連翹の花が咲いてた |
| トネリコ |
細雪 |
213 |
秦皮 |
秦皮のステッキ |
| シタン |
細雪 |
266 |
紫檀 |
紫檀製の支那式家具 |
| ツバキ |
細雪 |
268 |
椿 |
緑の地色に白い大輪の椿の花を絵羽附けにした日本服の盛装でいるのを、 |
| サクラ |
細雪 |
336 |
桜樹 |
一本の桜樹をも植えず |
| サクラ |
細雪 |
336 |
遠山桜 |
座敷から遠山桜をご覧になることです |
| ヤナギ |
刺青 |
11 |
楊 |
房楊枝をくわえながら |
| サクラ |
刺青 |
13 |
桜 |
若い女が桜の幹へ身を倚せて |
| ツバキ |
春琴抄 |
5 |
椿 |
見るとひと叢の椿の木かげに鵙屋家代々の墓が数基ならんでいるのであったが |
| マツ |
春琴抄 |
7 |
松 |
一と本の松が植えて |
| ヤナギ |
春琴抄 |
11 |
柳 |
知る如く花柳病の |
| ウメ |
春琴抄 |
54 |
梅 |
此処で梅見の宴を催し |
| ウメ |
春琴抄 |
54 |
梅 |
今日は梅見だっしゃないかいな一日位ゆっくりさしたげなはれ |
| ウメ |
春琴抄 |
54 |
梅 |
十数株の梅の古木を |
| ウメ |
春琴抄 |
55 |
梅 |
春琴を梅花の間に導いてそろりそろり歩かせながら |
| ウメ |
春琴抄 |
55 |
梅 |
わたい梅の樹だっせ」と道化た恰好をして |
| ウメ |
春琴抄 |
55 |
梅 |
「ほれ、此処にも梅がござります」と一々老木の前に立ち止まり |
| サクラ |
春琴抄 |
55 |
桜 |
姥桜の艶姿と |
| ウメ |
春琴抄 |
55 |
梅 |
ああ梅の樹が羨しい」と一幇間が奇声きを発したする |
| ウメ |
春琴抄 |
55 |
梅 |
老梅の幹を頻りに撫で廻す様子を見るや |
| ウメ |
春琴抄 |
60 |
梅 |
梅見の宴の後約一箇月半を経た |
| マツ |
春琴抄 |
73 |
松 |
せせらぎ松籟の響き |
| ウメ |
春琴抄 |
73 |
梅 |
水嵩の増した渓流のせせらぎ松籟(しょうらい)の響き東風(こち)の訪れ野山の霞梅の薫り花の雲さまざまな景色へ人を誘い、 |
| アオギリ |
少年 |
24 |
青桐 |
青桐の木立の下から |
| ウメ |
少年 |
25 |
紅梅 |
縁先の紅梅の影が映って |
| サクラ |
少年 |
38 |
桜 |
左近の桜右近の橘の下には |
| タチバナ |
少年 |
38 |
橘 |
左近の桜右近の橘の下には、人上戸の仕丁が酒を煖めて居る。 |
| ケヤキ |
少年 |
46 |
欅 |
年経る欅の根方に腰を下ろしたまま |
| カシ |
少年 |
48 |
樫 |
沼の側の樫の幹へ縛りつけ |
| ケヤキ |
少年 |
51 |
欅 |
例の欅の大木の葉が何処やら知れぬ |
| ヤツデ |
少年 |
52 |
やつで |
八つ手の葉や、欅の枝や、春日燈籠かや、 |
| ケヤキ |
少年 |
52 |
欅 |
欅の枝や |
| モモ |
痴人の愛 |
17 |
桃 |
髪も日本風の桃割れに結い |
| モモ |
痴人の愛 |
31 |
桃 |
その後は桃割れに結ったことは |
| バラ |
痴人の愛 |
54 |
薔薇 |
オミはソオファへ仰向けにねころんで、薔薇の花を持ちながら、それを頻しきりに唇へあてていじくっていたかと思うと、 |
| ツバキ |
痴人の愛 |
123 |
椿 |
それは私に、何か、椿の花のような、どっしりと重い、そして露けく軟かい無数の花びらが降って来るような快さを感じさせ、その花びらの薫りの中に、自分の首がすっかり埋まってしまったような夢見心地を覚えさせました。 |
| ウメ |
痴人の愛 |
167 |
梅 |
じめじめとした入梅の季節の |
| マツ |
痴人の愛 |
214 |
松 |
二人は暗い松の木蔭へ来ていましたが、そう云いながらナオミはそっと立ち止まりました。 |
| マツ |
痴人の愛 |
215 |
松 |
なぜなら私は、ちょうど彼等の出る路が、松林の多い、身を隠すのに究竟な物蔭のある、 |
| マツ |
痴人の愛 |
215 |
松 |
露のしたたる松の枝から、しずかに上る水蒸気にも、こっそり忍び寄るようなしめやかな香が感ぜられました。と |
| ウメ |
痴人の愛 |
277 |
梅 |
入梅の空が一時に |
| リンゴ |
痴人の愛 |
331 |
林檎 |
林檎の実のように白いことです |
| サクラ |
二人の稚児 |
194 |
山桜 |
山桜が咲き乱れて |
| スギ |
二人の稚児 |
194 |
杉 |
人通りの稀な杉の木蔭に腰をおろして |
| マツ |
猫と庄造と二人のをんな |
64 |
松の木蔭 |
時にはそうつと海岸へ持つて行つたり、蘆屋川の堤防の松の木蔭などへ捨てて来たりした。 |
| ポプラ |
猫と庄造と二人のをんな |
69 |
ポプラーの葉 |
裏の空地に聳(そ)えている五六本のポプラーの葉が白くチラチラ顫(ふる)へている向うに |
| ポプラ |
猫と庄造と二人のをんな |
119 |
ポプラーの蔭 |
いいあんばいに裏が空地になつているから、ポプラーの蔭か雑草の中にでも身を潜めて、 |
| クズ |
猫と庄造と二人のをんな |
125 |
葛の葉 |
葛の葉が一杯に繁つていて、その葉の中でときどきピカリと光るものがあるのは、 |
| カズラ |
猫と庄造と二人のをんな |
130 |
葛の葉 |
彼は慌てて葛の葉の繁っている間へ、筍の皮を開いて置いて、 |
| ポプラ |
猫と庄造と二人のをんな |
140 |
ポプラー |
僕あのポプラーの蔭に隠れてましたよつてにな。」 |
| シタン |
秘密 |
100 |
紫檀 |
四角な紫檀の机へ |
| マツ |
母を恋うる記 |
216 |
松 |
長い長い松並木が眼のとどく限り続いて |
| マツ |
母を恋うる記 |
218 |
松 |
この松並木の月の色が |
| マツ |
母を恋うる記 |
218 |
松 |
長い長い松原の右の方には |
| マツ |
母を恋うる記 |
219 |
松 |
左側の松原に並行して |
| マツ |
母を恋うる記 |
219 |
松 |
ざあーッと云う松風の音の間から |
| マツ |
母を恋うる記 |
219 |
松 |
同じような松の縄手が |
| マツ |
母を恋うる記 |
220 |
松 |
松の葉と云うものが緑色であったことを想い出した。 |
| マツ |
母を恋うる記 |
220 |
松 |
ほんとうに、松の葉の色さえ忘れて居たくらいなのだから |
| マツ |
母を恋うる記 |
220 |
松 |
黒い松の樹とを長い間 |
| マツ |
母を恋うる記 |
220 |
松 |
今通って来た松原も |
| マツ |
母を恋うる記 |
220 |
松 |
幾度か松並木の間に |
| マツ |
母を恋うる記 |
221 |
松 |
松並木の間から |
| マツ |
母を恋うる記 |
222 |
松 |
ちょうど松並木のつきあたりに見えている |
| マツ |
母を恋うる記 |
222 |
松 |
向う側の大木の松の根本にまで |
| マツ |
母を恋うる記 |
226 |
松 |
さあッさあッと云う松風の音が |
| マツ |
母を恋うる記 |
226 |
松 |
鬱蒼とした松の枝に遮られて |
| マツ |
母を恋うる記 |
226 |
松 |
大きな松の木の林が頂上まで |
| マツ |
母を恋うる記 |
226 |
松 |
この街道の松並木と同じような |
| マツ |
母を恋うる記 |
226 |
松 |
例の松風の音が颯々と聞こえている |
| マツ |
母を恋うる記 |
227 |
松 |
うっかりすると松林へ紛れ込んで |
| マツ |
母を恋うる記 |
227 |
松 |
まだ松林は尽きないけれど |
| マツ |
母を恋うる記 |
227 |
松 |
ちょうど正面の松林が疎らになって |
| マツ |
母を恋うる記 |
227 |
松 |
この松林の奥へまでも |
| マツ |
母を恋うる記 |
228 |
松 |
青白い月が松の葉影をくっきりと |
| マツ |
母を恋うる記 |
228 |
松 |
見覚えのある枝振りの面白い磯馴松が |
| マツ |
母を恋うる記 |
228 |
松 |
先刻松林の奥から見えたのは |
| マツ |
母を恋うる記 |
230 |
松 |
自分もあの磯馴松や砂浜のように |
| マツ |
母を恋うる記 |
231 |
松 |
もう少しで松の根方を濡らしそうに |
| マツ |
母を恋うる記 |
231 |
松 |
今度は松の影を数えながら |
| マツ |
母を恋うる記 |
231 |
松 |
何本も先の磯馴松の奥の方からか |
| マツ |
母を恋うる記 |
231 |
松 |
松は従であるかのように感ぜられる |
| マツ |
母を恋うる記 |
231 |
松 |
松は消えても |
| マツ |
母を恋うる記 |
231 |
松 |
松と影とは根元のところで |
| マツ |
母を恋うる記 |
231 |
松 |
鮮かな磯馴松の影が |
| マツ |
母を恋うる記 |
233 |
松 |
地上には私と松の影より外に |
| マツ |
母を恋うる記 |
234 |
松 |
路には磯馴松があって |
| モミジ |
盲目物語 |
135 |
もみじ |
あきはもみじかり |
| サクラ |
盲目物語 |
135 |
さくら |
もはやほっこくもさくらのはながちり |
| サクラ |
盲目物語 |
135 |
さくら |
もはやほっこくもさくらのはながちり |
| ナシ |
盲目物語 |
194 |
梨 |
梨花一枝雨を帯びたるよそほひの、雨を帯びたるよそほひの」と、 |
| ヤナギ |
盲目物語 |
195 |
柳 |
未央の柳のみどりも、これにはいかでまさるべき、 |
| ヤナギ |
卍(まんじ) |
9 |
柳 |
それに楊柳観音の姿さしまして |
| ヤナギ |
卍(まんじ) |
16 |
柳 |
この顔が果して楊柳観音の尊容に |
| キリ |
卍(まんじ) |
40 |
桐 |
あたしは今窓の外の桐の花にふりそそぐ雨の音をききながら、 |
| プラタナス |
卍(まんじ) |
41 |
プラタナス |
運動場のプラタナスの下に立っています |
| プラタナス |
卍(まんじ) |
57 |
プラタナス |
運動場のプラタナスの蔭に待ってますと |
| サクラ |
卍(まんじ) |
75 |
桜 |
あそこに汐見桜云う |
| サクラ |
卍(まんじ) |
75 |
桜 |
名高い桜あるついその近所なんでして |
| マツ |
卍(まんじ) |
76 |
松 |
片ッぽ側が大きな松のたあんと |
| サクラ |
卍(まんじ) |
82 |
桜 |
台所へ桜ん坊のジェリー拵えてる時でした |
| ナツミカン |
卍(まんじ) |
97 |
ナツミカン |
ちょうどナツミカン売ってるのん買うて |
| ミカン |
卍(まんじ) |
97 |
蜜柑 |
前の時蜜柑転ばしたりしたのん |
| ウメ |
卍(まんじ) |
118 |
梅 |
又「梅園」の前まで |
| ウメ |
卍(まんじ) |
118 |
梅 |
必要なこと出来たら「梅園」で待ち合いしまひょ |
| さくら |
蓼喰う虫 |
20 |
彼岸ざくら |
三月末の彼岸ざくらが綻びそめる時分のことで、きらきらしい日ざしの底にまだ何処となく肌寒さが感ぜられたが、 |
| ツバキ |
蓼喰う虫 |
76 |
椿の花 |
瑠璃色の古伊万里の壺に椿の花の活いけてあるのが、 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
79 |
梅の枝 |
窓を見上げている高夏の顔は、梅の枝に遮ぎられていた。 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
80 |
梅の樹 |
庭には梅の樹が五六株あった。以前この辺が百姓家の庭であった頃からのもので、 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
80 |
梅の幹へ |
その梅の幹へそれぞれつながれているのである。 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
80 |
梅の枝 |
梅の枝が幾つも交錯しているのではっきり見定めにくいけれど、 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
82 |
梅の樹 |
要はヴェランダの日だまりを動くのが厭だという形で、梅の樹の方へ立って行く二人に云った。 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
82 |
梅の枝 |
繁みの向うの梅の枝がざわざわと揺ゆらいで、ピオニーの方が突然ひいひいしゃがれ声を立てた。 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
102 |
梅の木 |
梅の木の間を小鳥が一羽、枝から枝へ飛び移っている。 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
102 |
梅の向う |
梅の向うの野菜畑で、じいやがフレームの蓋を開けて、 |
| シタン |
蓼喰う虫 |
104 |
紫檀のチャブ台 |
自分は紫檀のチャブ台の前にすわりながら、 |
| クワ |
蓼喰う虫 |
105 |
桑の茶箪笥 |
台所の方へ云いつけておいて、うしろの桑の茶箪笥をあけた。 |
| リンゴ |
蓼喰う虫 |
112 |
三つの林檎 |
「ユーナン王とドウバン聖者の話」、「三つの林檎の話」、 |
| ヤナギ |
蓼喰う虫 |
132 |
岸の柳 |
ささえられたる北風に、身はままならぬ丸太ぶね、岸の柳に引きとめられて、 |
| カラマツ |
蓼喰う虫 |
152 |
北海松 |
焼けた跡に建てられるのは北海松(カラマツ)や米材の附け木のように白っちゃけた家か |
| ウツギ |
蓼喰う虫 |
153 |
つぎの花 |
丸瓦の上からのぞいているうつぎの花を眺めたとき、 |
| ケヤキ |
蓼喰う虫 |
154 |
欅の看板 |
「うるし」「醤油」「油」などと記した文字の消えかかっている欅の看板、土 |
| ミカン |
蓼喰う虫 |
160 |
蜜柑 |
村の子供たちが駄菓子や蜜柑をたべながら芝居の方はそっち除のけに、 |
| センダン |
蓼喰う虫 |
178 |
栴檀 |
庭には紫の花をつけた大きな栴檀の樹があって、その樹の蔭のじめじめしたところに、 |
| サクラ |
蓼喰う虫 |
180 |
姥桜 |
そしてさすがに女将株の貫目もあり、活気もあり、何処やらにまだ姥桜の色香さえもあって、 |
| スギ |
蓼喰う虫 |
208 |
北山の杉 |
そう念を入れて拭き込みもしなかった北山の杉や栂の柱が年相応のつやを持ち出して、 |
| トガ |
蓼喰う虫 |
208 |
栂の柱 |
そう念を入れて拭き込みもしなかった北山の杉や栂の柱が年相応のつやを持ち出して、 |
| チョウジ |
蓼喰う虫 |
223 |
丁子 |
あのお湯は丁子の匂いで胡麻化してあるので幾日目に換えるのだか分らないと云って、 |
| スギ |
蓼喰う虫 |
223 |
杉の葉 |
いつも杉の葉の青々としたのを朝顔に詰めるのはいいとして、 |
| チョウジ |
蓼喰う虫 |
223 |
丁子風呂 |
主の方は又「うちの丁子風呂」と云うのを自慢にして、 |
| チョウジ |
蓼喰う虫 |
223 |
丁子 |
その上丁子を煎じてあるのが、垢だらけに濁った薬湯のような連想を起させるのである。 |
| チョウジ |
蓼喰う虫 |
224 |
丁子の湯 |
ざっとシャボンも使わずに汗を洗い落してから丁子の湯の中に浸りきっていたが、 |
| カエデ |
蓼喰う虫 |
224 |
楓の青葉 |
楓の青葉が日中よりは却って冴えて織り物のような鮮やかな色を覗かせている。 |
| チョウジ |
蓼喰う虫 |
224 |
丁子 |
彼女の話だと、丁子も近頃はエッセンスを売っているから、 |
| チョウジ |
蓼喰う虫 |
226 |
丁子風呂 |
「なあに、丁子風呂もたまには変っていていいですよ」 |
| ビワ |
蓼喰う虫 |
228 |
枇杷 |
あとはあっさり茶漬にしてから、食後に枇杷を運んで来たお久は、 |
| ウメ |
蓼喰う虫 |
232 |
梅が香 |
さっきから微かに香っているのは大方あれに「梅が香」が薫じてあるのであろう。 |
| サクラ |
帮間 |
62 |
桜 |
桜が満開で |
| サクラ |
帮間 |
80 |
桜 |
裏地に夜桜の模様のある |